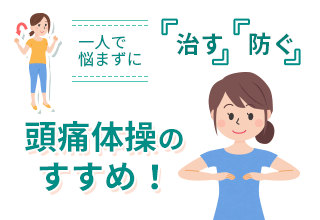毎日続く頭痛
- 監修:
-
慶應義塾大学医学部 神経内科 専任講師滝沢 翼 先生
2025年9月作成
毎日頭痛が続くと、日常生活への影響が大きいだけでなく、それが何らかの病気のサインではないかと不安に思われることもあると思います。本ページでは、毎日続く頭痛の原因、対処法、そして受診のときのポイントについて解説します。
頭痛が毎日続くことは何かの病気のサインなの?
頭痛が毎日続いたり、いつもの頭痛と違ったりするときには、元からある頭痛が長引いている場合もあれば、別の頭痛が組み合わさっていることもあり、原因はさまざまです。そのなかには、頻度は高くないものの、感染症や腫瘍、外傷など他の疾患が原因となって起こる「二次性頭痛」の可能性もあり、見逃すと命に関わることもあります。
不安を取り除くためにも、もし頭痛が毎日続く場合には、早めの受診をご検討ください。
毎日続く頭痛の主な原因
毎日続く頭痛には、他の疾患が原因となっているもののほかにも、さまざまな原因があります。
元からある頭痛の慢性化
片頭痛や緊張型頭痛の症状がある方で、徐々に頭痛の頻度が増えてきた場合は、元の頭痛が慢性化している可能性があります。受診の際には、普段の頭痛がどのような症状で、どれくらいの頻度で起こっていたのかの情報があると、診断の助けとなります。
薬剤の使用過多による頭痛
頭痛持ちの方が、長期間にわたり月に10日もしくは15日以上、頭痛薬を服用している場合は、薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を起こしている可能性があります。
急に毎日頭痛が起こることも
一方で、前に述べた「二次性頭痛」のほかにも、頭痛持ちではない方が、ある時から急に毎日頭痛が起こるケースもあります。「新規発症持続性連日性頭痛」のような頭痛が知られています1)。
不規則な睡眠や食事
睡眠の過不足や不規則な食事は頭痛の原因となることがあります。規則正しい睡眠と食事を心がけることが大切です。特に空腹状態が続くことは片頭痛を引き起こす要因となるため、3食きちんととることが重要です。
精神状態・ストレス
ストレスと頭痛は非常に関係が深く、頭痛が毎日続くことにもつながります(こころと頭痛)。
子どもの場合は、勉強や友人関係といった学校生活での悩みが頭痛の原因となるケースが多く見られます。
大人では、仕事でのストレスが毎日続く頭痛につながるケースが少なくありません。コロナ禍では、ライフスタイルの急激な変化によるストレスが頭痛を悪化させたケースも報告されています。
毎日続く頭痛への対処法
専門医への受診と相談
頭痛が毎日続く場合は、まずはかかりつけ医にそのことを伝え、できれば頭痛に詳しい医師や頭痛専門医を受診することをご検討ください。日本頭痛学会のホームページに掲載されている認定頭痛専門医の一覧を参考にできます2)。
これまでに頭痛の画像検査を受けたことがない、もしくは以前に検査を受けてから期間が空いている方であれば、MRIやCTなどの画像検査で、頭蓋内に異常がないかを調べることができます。受診により、他の疾患が原因となっている可能性を除くことができれば、頭痛の治療薬やセルフケアによる対処も可能になります。
薬の服用について
医師の診断に応じた薬を服用することで、症状に対応したり、予防を行うのが基本的な対処法です。
元々ある頭痛が慢性化したような場合には、元の頭痛に対する治療薬が効くケースが多いです。一方で薬剤の使用過多による頭痛には、服用回数を抑える方向で対処することもあります。
生活面の工夫
ご自身で行える生活面の工夫には以下のようなものがあります。
- 睡眠:規則正しく、寝すぎず、かつ寝不足にならないように注意します。就寝時間を一定に保つことが望ましいです。
- 食事:空腹状態が続くのを避けるように、規則正しく3食とることが重要です。チーズやチョコレートなど頭痛を引き起こすような特定の食品を避けるべきといわれることもありますが、個人差が大きいため、あまり神経質になる必要はありません。バランスの良い食事を心がけましょう。
- 運動:定期的な運動は頭痛の予防に繋がるため、普段から適度な運動を心がけましょう。ただし、片頭痛の発作中は体を動かすと悪化するので行わないようにしましょう。
- ストレス管理:ストレスは頭痛の原因となるため、ストレスを適切に管理することが重要です。仕事の負荷軽減や休職を勤め先に相談するときは、医師の診断書を提出するのも一つの方法です。
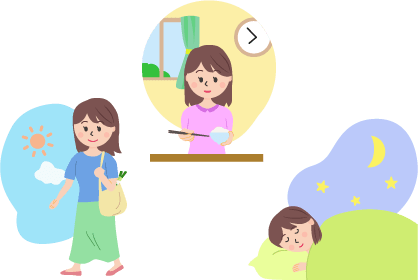
受診のときのポイント
いつ受診するか
痛みの程度にもよりますが、以下のような場合には、早めの受診をご検討ください。
- 頭痛が強くて日常生活に支障がある
- 頭痛が悪化している
- 頭痛がいつもと異なる
- 症状の改善なく3日を超えて頭痛が続く
また、頭痛以外に気になる症状がある場合は、頭痛の痛み・頻度が軽度でも早めの受診をご検討ください。
受診時に何を伝えるか
問診の時に以下の情報を伝えると、診断と治療の参考になります。
これらの項目は医療機関で渡される問診票に記載がある場合も多いですし、自身でまとめたメモや後からご紹介する頭痛ダイアリーを持参すると症状を伝えやすくなります。
- 頭痛の具体的な状況
- いつから頭痛が続いているか
- 頭痛が突然はじまったか
- 頭痛のパターンに変化があったか
- 痛みの性質(ズキンズキンと脈打つよう、締め付けられるよう、など)
- 痛む場所(頭の片側だけか両側か、前頭部か、側頭部か、頭頂部か、後頭部か、目のまわりや目の奥か、頭全体か)
- 予兆があるか(頭痛の前に生あくびや肩こりなど)
- 痛みが続く時間(半日程度で治まる、1日続く、など)
- 毎日続くようになる前にも頭痛があった場合は、その状況
- 症状・エピソード
- 発熱
- 体重の減少
- 何かに強くぶつかった
- 感覚や見え方がおかしい
- 力が入りにくい …など
頭痛とは関係しないように思える症状・エピソードであっても、他の疾患が原因となっている可能性を検討するうえで参考になります。あくまで一例として、以下のようなものです。
- 服用している薬
市販薬を含め、服用している薬の種類と回数
- 生活習慣
睡眠時間(よく眠れているか)や食事の状況(食欲に変化はないか)、運動習慣など
- 精神状態・ストレス
仕事や家庭でのストレス、不安感、食欲低下、不眠など
頭痛ダイアリーの活用
頭痛の症状を医師に伝えるのに有用な手段の一つが、頭痛ダイアリーです。頭痛ダイアリーには、頭痛の頻度、性質、強さ、原因、服用した薬の効果などを記録でき、頭痛のパターンを把握する助けとなります。ただし、「頭痛ダイアリーのすべての記入欄を埋めなければいけない…」と無理をする必要はありません。また、紙の頭痛ダイアリー以外にも、アプリ形式もありますし、簡易的なメモであっても十分に診療の助けとなります。ご自身が取り組みやすい方法からはじめましょう。

- <参考>
-
- 1)日本頭痛学会・国際頭痛分類委員会:国際頭痛分類 第3版, 医学書院, 2018.
- 2)日本頭痛学会,〈認定頭痛専門医一覧〉(https://www.jhsnet.net/ichiran.html) (2025年8月1日閲覧)